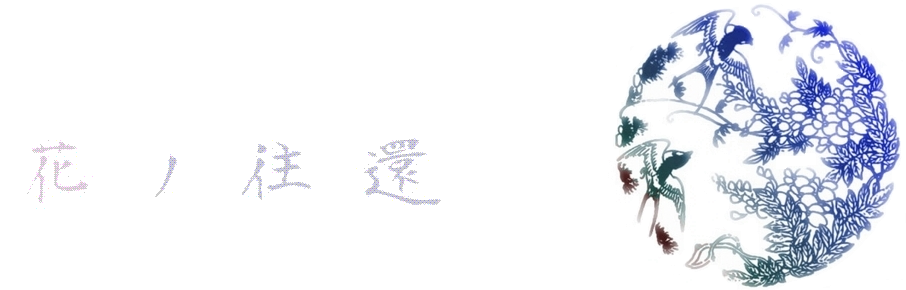九博で開かれていた特別展の感想です。
*展示室内の画像は九州国立博物館より提供していただいたものです。
室内に入ると、まず富士山や夫婦岩などの写真がタペストリー仕立てで展示されていました。
絹垣に見立てた薄布ごしに見るようになっていたのですが、正直空き店舗のウィンドウディスプレイみたいだと思ってしまいました。←すみません[:汗:]。
神域をうまく表現しているとは思いましたが。
↓

紹介ゾーンとしてそれなりに成立していましたが、これだけのスペースが空いているのはもったいなかった。
そこを抜けると、山ノ神遺跡や沖ノ島の祭祀遺物などが展示です。
↓

古墳時代、拝殿も神殿もなく、まだ仏教もなかったころの祀りの有り様が伺えます。
鏡やミニチュアが捧げられている所などは、古墳や王墓の副葬品に通じるものを感じました。
御嶽(うたき)からの出土品にもびっくり。
第二尚氏時代の埋納品とのことですが、勾玉も埋納されていました。
ここはとてもよかったです。
今回の展示の根本となる思想が表れているコーナーだったと思います。
それからは、垂玉宮縁起絵を見たり、「国宝天神さま展」の時の展示品と再会したり、七支刀のレプリカをしげしげと眺めたりしながら会場を進みました。
↓

見えている御輿は手向山八幡宮の手害会で実際に使用されたものだそうです。
一条通をずうっと行って転害門に突き当たるあの通りを、この神輿も行ったのかと思うと感慨もひとしおでした。
おや、と思ったのは大坂住吉大社の面楯。南方系の感じがします。
↓

ベトナム展で見た鬼瓦に似ている、と思いました。13~14世紀のものだそうです。
熊野夫須美大神座像はさすがの迫力でした。
が、写真であっても載せるのが憚られるので略します。
(九州会場のポスターになっています。気になる方はそちらをご覧下さい。)
それよりも、私が気になったのはこちらの神像です。
こちらもちょっと載せるのが憚られるのですが、こういう機会は無いでしょうからご紹介。
↓

展示後半は、由緒ある神社の木像が圧巻でした。
何か畏れ多くて、こんな風にみていいものかハラハラし通しでしたけれど。
(絹垣を巡らすなら、パネルにではなくこちらの方にこそではないかと思いました。)
熊野速玉大社・松尾大社・高野神社といった、錚錚たる古社の神像を見ることが出来るなんてもうないかもしれませんね。
貴重な体験でした。
話は変わりまして。
関連イベントの「神社の伝統」を見に行きましたので、そちらの感想も書いておきます。
「祝おう 遊ぼう 神様と」のコピーの通り、2月1日の九博はとても楽しかったのです。
ホールは木の柱と注連縄で舞殿が拵えてあり、齋場らしい雰囲気が漂っていました。
↓

ここで、念願だった瀬高町大江天満神社の幸若舞も見ることが出来て大満足。
↓

大村神楽の「綱駈仙」(だったと思います)はその名の通り観客席の中を走る走る。子供が泣こうがお構いなしです。楽しかった。
↓

また、エントランスと続きになっていて、そちらは玉垣風なセッティングでした。
(画像はそこで行われていた北野天満宮風流)
↓

北野天満宮の子供達が可愛かったので、動画を少し切り出しました。5秒ほどですがご紹介。
↓ (お使いの環境によっては表示されないかもしれません。)
こうしてみると衣装や小道具が時代を反映していて興味深いです。
蜷城の獅子舞はシュロ、北野天満宮の風流では大人(男性)は裃でした。
豊前神楽では小道具に聴診器やアルミの脚立があったりして、そのあたりの自由さが面白かったです。
最後に、展示目録はよく確認しとこうねという話をちょっとだけ。
実は、開催前何かでこのチラシを見て、てっきり細見美術館の金銅春日神鹿が来ると思っていた私。
↓
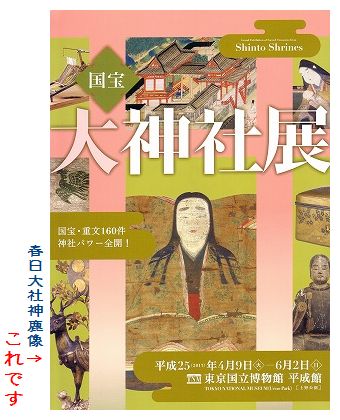
これ、東博だけの展示だったのですね。七支刀も。
もう一度見られると思っていたので、それが残念でした。