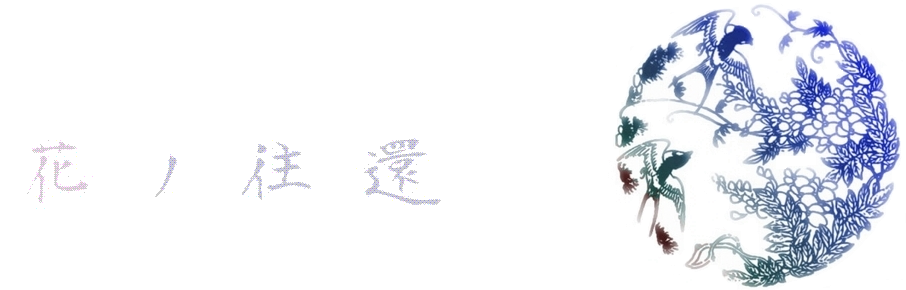九州国立博物館で開催中の特別展の感想です。
台北にある故宮博物院の文物が、ついに日本に来ましたね。
私が見た時は日本での展示は望めない状況でしたので、感慨深いものがあります。
画像は会場入り口にある、展示の意義やいきさつが述べられたパネルです。
開館記念特別展以来の真剣さで読んだかもしれません。
↓
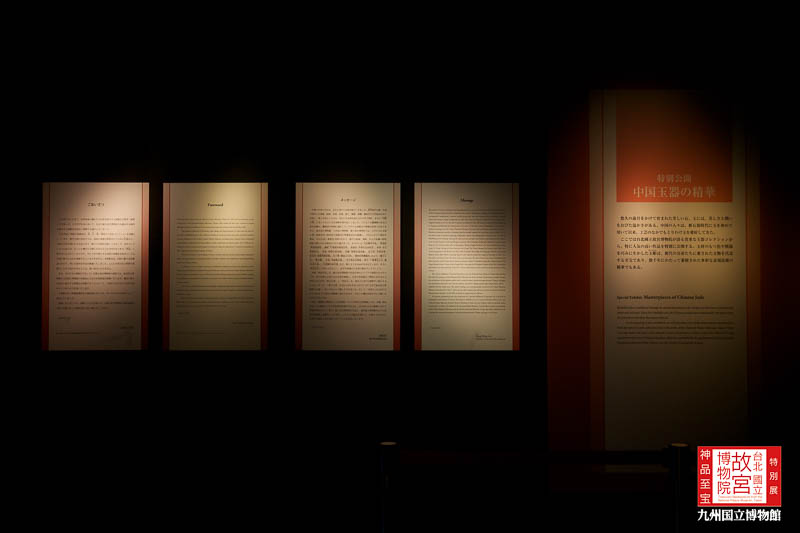
*展示室内の画像は九州国立博物館から提供していただいたものです。
今回日本向けにセレクトされたことでスポットが当たった文物は、一度見ているはずなのに新鮮でした。
書画には思いがけず“懐かしさ”を感じましたし、“天を祀る思想”の脈々とした流れを再認識しました。
日本古美術の展示だと言われても違和感のないこの光景。
↓

中・近世に日本の画家たちが憧れ学んだ世界がそこにありました。
それは今も私たちが親しんでいる美ですから。懐かしさを感じても当然かもしれません。
こちらは「天地人 三連玉環」。
この世界観も私たちにはなじみのものですね。
↓

宇宙独楽のようなものの左上にほんのちょっとだけ「玄宗皇帝玉冊」も写っています。
唐の玄宗が「封禅の儀」を行った時の冊です。
天を祭る資格の大切さが、歴代の皇帝の中に生きていた証ですね。
今回来るとは思っていませんでしたので、また見ることができて嬉しく思いました。
そうでありながらこんなことするなんて~、と思ったのが。「鷹文玉圭」。
↓

新石器時代晩期~商前期に神との交流のための媒体として用いられた礼器。
清の乾隆帝が追加で詩を彫らせたのですが、上下を逆さにして彫ったのだそうです。
単純に間違えた?古からの価値観をふまえた上で新しい何かを生もうとした?
皇帝といえど、貴重な紋様を上書きするなんて、と思ってしまいました。
展示されている青銅器の中に、故宮博物院を象徴しているなと思ったものがありました。
こちらの画像に見える、そっくりな二つの儀尊です。
↓

右端のものが戦国時代のもので、真ん中のものが元~明時代のもの。
右は出土品でいわばオリジナル。真ん中はその模造品なんですね。
「倣古」と言う考えのもと、古い時代のもののコピーが北宋以降作られたのだそうです。
13~14世紀にこういう精神(いわば中国のルネッサンス)があり、その精神を表すものとして伝えられたところが故宮文物ならではだと思いました。
その他では以下の三つが印象に残りました。箇条書きにします。
その1、秋林群鹿図軸
↓

びっくりしました。遼のものだそうです。紙幅類は残るのが難しいのに、すごい!
遼と言えば3年前の「契丹」展を思い出しますが、あの時の展示では見なかった類のものですね。
(展示は出土品中心でしたし、当然ですが。)
遼(契丹)の文化にこんな一面があって、宋とこのような交流があったとは思いがけないことでした。
よくぞ日本に来てくれました。
その2、青花雲龍唐草文五孔壺
↓

一瞬「メノラー?」かと思いました。
五爪の龍が正面を向いているお馴染みの意匠ですが、とても変わった形をしています。
メノラーではないにしろ、これ、私には燭台を模したようにみえるのですがどうでしょう?
清時代に景徳鎮窯で焼かれたものとのこと。
この時代、キリスト教や西洋文明の影響があってもおかしくはないですよね。
おかしいかしら?
汝窯の青磁より気になりました。
その3、新嘉量
↓
(※博物館から提供していただいた画像の中になかったので、どんなものか気になる方は「新嘉量」で検索されてください。故宮展の公式ページにもあります。)
嘉量とは度量衡の標準器で、新嘉量とは”新の王莽(おうもう)が始建国元年(西暦9)に新しく制定した度量衡の基準器”のこと。
そして”清の乾隆帝は新嘉量を正統なる権力の象徴として重要視し、これにならった量器を鋳造”したのだそうです。
(” ”内は東京国立博物館のページより引用しました。)
王莽が開いた「新」はとても短命で、簒奪者が開いた徒花のような政権だと思っていましたが、2000年以上受け継がれるようなものを残していたのですね。
地元福岡でも新の貨布が出土していますし、一体どういう時代だったのかますます興味が湧きました。
また、複製を作らせたところに、乾隆帝の漢民族へのまなざしも伺えます。
異民族と漢民族、中国の歴史の面白さ不思議さ、など感じさせる逸品でした。
伝世品の意味を改めて考えさせられ、とてもよかったと思います。
これをセレクトしてくださってありがとうございました。
以上、特別展の感想でした。
例年この時期、四階で茶の湯に関するトピック展示が開かれていたのですが、今年はなかったので少し寂しく思いました。(そのかわり、もっとタイムリーな企画展が催されていたのですが。)
茶の湯に関する展示も、またいつか企画していただけたらと思います。
次は百済ですね。楽しみです。