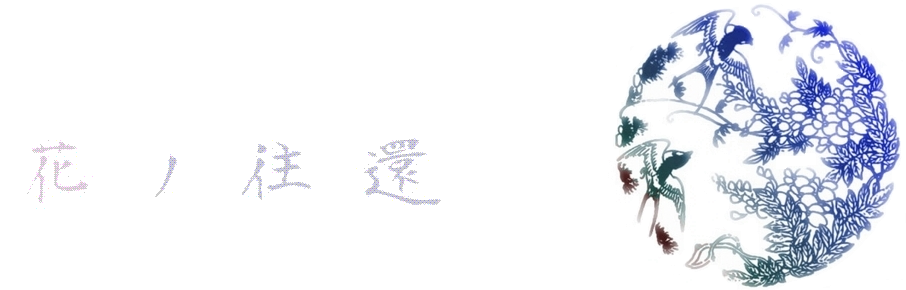春日市の婿押し祭を初めて見に行きました。
季節の風物として、ローカルニュースでは毎年このシーンが放送されますね。
↓

今回知ったのですが、これは祭りのほんの一部でした。
祭事は左義長への点火から始まります。
↓

締め込み姿のこども達による樽競り、花婿花嫁の挨拶などが続いた後に、池に入って縁起物の樽を競ります。
大人になっていきなりではなく子供の頃から練習してるのですね。
そして樽競りが決着したら終わりではなく、その後近くの川にお潮井を取りに行くのです。
え、お潮井?川に?と思いました。
(詳しくは春日神社の公式ページでどうぞ。)
私が知らなかっただけで、よくあることなのでしょうか?
この祭事で大事なのは、新年の禊ぎをすることのようでした。
気になって後日その場所を訪ねてみました。
すると、「御潮井橋」という名前の橋がありました。
朱の擬宝珠つき欄干が見えているのがそうです。
橋の名前になっているほど大切な場所なのですね。
河川名としては牛頸川になるのですが、御祓川と呼ばれているそうです。
対岸に見えているこんもりとした茂みは「奈良松山」というのだそう。奈良?ますます不思議。
↓


橋のたもとには祠がありました。九郎天神とあります。供老とも黒男とも書くそうです。武内宿祢なのかしら?
↓

ご神体は三角形の石でした。側にはもみすり石という溝がたくさんある石もありました。
天文関係のような気もします。
春日市お宝文化百選のページ→九郎天神社(石仏)もみすり石
近くには地録天神・三郎天神もあります。
三社とも春日神社の末社ということですが、こちらの方が古いのではないかしら?という気がしました。
そもそもなぜ天智天皇はここに神籬をおいたのでしょう?
婿押し祭りからだんだんそれていきますが、興味が尽きません。
なにか記録がないか探してみようと思いました。