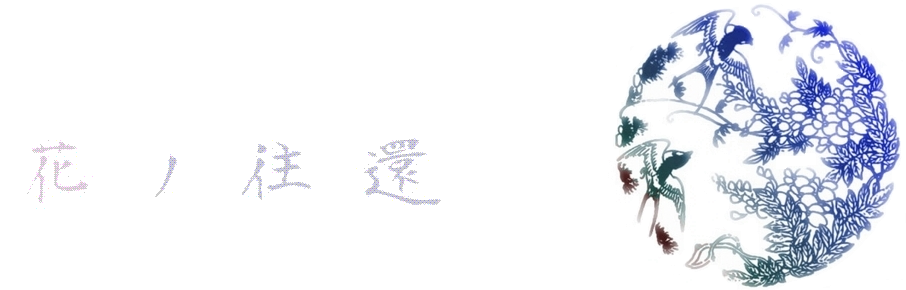NHKの特集番組を見ていたら、高分解能古気候学と言う研究をされている方が登場。
AD147年は、過去2000年間のうち突出して雨の多い年だったことを話されていました。
概略はこちらのページでも見ることが出来ます。→高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索
このときの洪水で登呂遺跡が埋没したと考えられるそうです。
また、弥生時代の遺跡が急に姿を消した要因ではないかという話でした。
あれ?147年と言えば、倭国大乱の年。(『後漢書』卷85 東夷列傳第75)
番組では、大洪水の前後は気候が荒れるということでした。
大洪水の数年後には大干ばつがあったことも先の資料から読み取れます。
倭国大乱の原因については、王位継承争いであったり寒冷期で作物がとれなかったりしたためなどが言われていますが、こんな大水害と大干ばつが起こっていたのなら国中が大混乱になったのも当然だったのではないでしょうか。
食料を求めて争いになったり国外に出たりしたというのも頷けます。
気象学と考古学、面白いです。